どうも、けーよーです。公務員を目指している学生の方や、今現在社会人として生活している中で転職を考えていて、転職先に公務員を検討している方に、元国家公務員である私自身の経験談や実態、役に立つ情報を発信していきます。
前回は重点的に勉強するべき科目や、各科目はどういったものなのか説明をさせていただきました。今回もその続きをお話していこうと思います。
人文科学について
試験に出される科目のひとつに、人文科学という科目があります。これはいわゆる日本史や世界史の複合で、織田信長が何をしたとか、ナポレオンは何をしたとかの選択問題になります。皆さんお分かりのとおり、暗記科目になります。ですから、純粋にどれだけの時間を費やしたかがそのまま得点率につながってきます。自分は暗記科目は苦手ではなく、むしろ得意なほうでしたので苦ではなかったです。
出題数としては、1試験に2~3問ですが、多いときは4~5問ほど出題されます。公務員試験の職種ごとの出題比率の違いなどはほとんどなく、純粋にその年度ごとの試験作成担当の気まぐれによって変わってきます。全く出題されないということはないですが、年度ごとのばらつきがあり、決して捨ててはいけない科目です。
この人物がどういう人で、何をしたかなどを覚えようとすると、途方もない時間がかかります。私がしていた勉強法を皆さんしているかもしれませんが、紹介します。
例えば織田信長は楽市楽座をした人で、本能寺の変で討ち取られてますよね。織田信長の生涯を丸ごと覚えようとしてもキャパオーバーしてしまうし、とても時間がかかりますよね。なので、人物ごとのキーワード表みたいなものを作成していました。
織田信長→桶狭間の戦い、楽市楽座、本能寺の変 といった、その人物がどんな物事を起こしたのかを簡単にまとめていくんです。そうすれば時間も丸ごと覚えるよりは少なくて済みます。そして違う問いに対してはしっかり引っ掛かりをもって対処することもできます。
基本的に、下記5つの選択肢の中から正しいものを1つ選べ、という出され方をします。豊臣秀吉は刀狩をしたのち、本能寺の変で明智光秀に討ち取られた、という文言があったとします。先ほどの勉強法であれば、本能寺の変は織田信長だったよな…じゃあ違うな、というふうに引っ掛かりを持つことができますよね。
こちらの人文科学も、縄文時代から明治くらいまでの出来事を幅広く問われます。その中で一つ一つの出来事や人物の特徴を覚えようとしても、とてもじゃないですけど時間が足りないんです。一番最初の記事でもお伝えしましたが、広く浅く勉強するということが鍵になってきます。そのため、上記の最低限の内容をキーワード・単語化して覚えていくというのがとても有効です。そうすることで、一つの物事や、人物についての勉強時間を短縮することができる上に、幅広い範囲での学習をすることが可能になります。
その他
ほかにも、英文長文の和訳などもありますが、こちらについては出題数は1問、多くて2問ほどです。覚えなければいけない単語や英文のルールが膨大なわりに、勉強してもあまり点数を伸ばすことができないので、はっきり言って捨ててしまっても構いません。この英文の和訳として適切なものを次の5択から選びなさいという問われ方をします。今まで学校の授業で習った、覚えている単語の意味をかき集めて、ニュアンス的にこの和訳が正しいのかな?と思う選択肢を選ぶ、外れたとしても1~2点なので、正答できたらラッキーと考えるのがいいと思います。
また、長文であるため、なんとなくのニュアンスを理解するのにある程度読まなければなりませんが、読むこと自体にも時間がかかります。ほかの数的処理や判断推理など、出題数が多く、得点しておきたい科目をまずは解き、余った時間で和訳をするのがいいでしょう。最悪、時間が足りなければ、神頼みで回答をするのもいいと思います。ほかに時間をかけるべき科目がありますからね。
自分の場合は全く勉強していませんでした。(笑)それに加えて、中学高校時代まともに勉強をしてこなかったため、覚えている単語もかなり少なかったので、正答率はかなり低かったです。ですがそれでも国家公務員である税務職員採用試験に合格することができていますので、まあなんとかなるということです。(笑)
今回のまとめ
今回は、人文科学とその他英文和訳の勉強法等の記事を書かせていただきました。公務員試験では、広く浅く勉強すること、解く問題の優先順位を決めることが大事になってきます。次回は採用後の1年間の研修について、思い出話も兼ねながら記事にさせていただこうかなと思っています。どのような場所であったか体験談をもとにお話しできれば、より自分の進路や転職先についてのイメージがつかめてくると思います。
それでは、ありがとうございました。

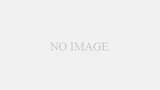
コメント